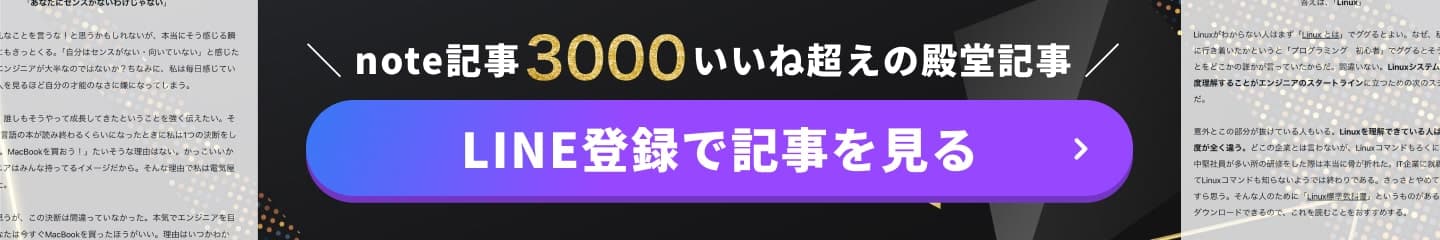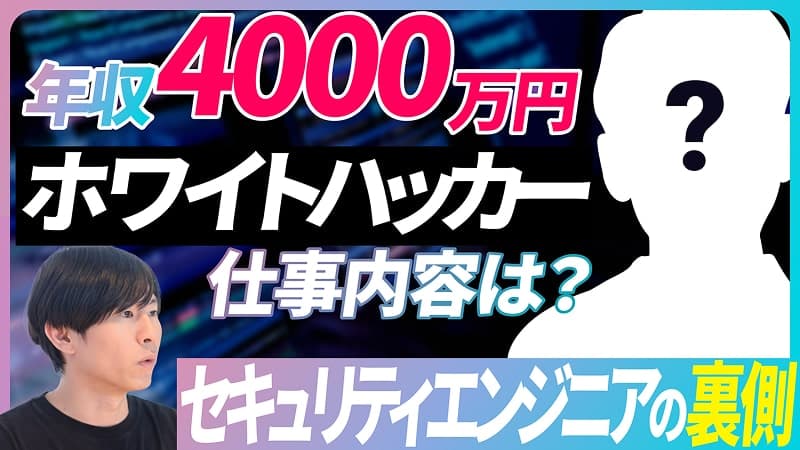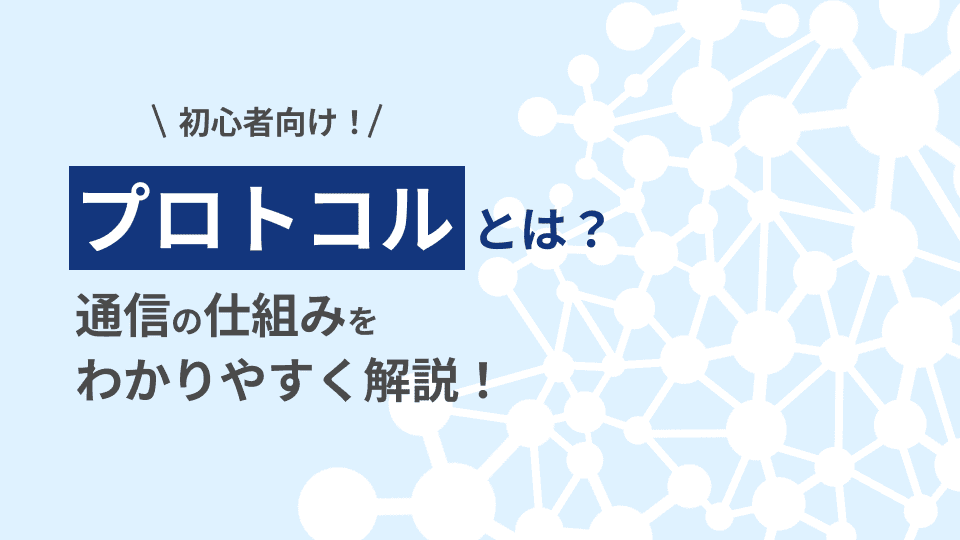
はじめに
現代のデジタル社会では、Webサービスやアプリケーションなどが日常的に利用されています。これらの裏側では、コンピュータ同士が常にデータをやり取りしています。この通信を正確かつ安全に行うために欠かせないのが、「プロトコル(Protocol)」と呼ばれる技術的なルールです。
しかし、このプロトコルについては「イメージしづらい」「難しそう」と感じる人も多いのではないでしょうか。本記事では、そんな方に向けて「プロトコルとは何か」「なぜ必要なのか」「どのように使われているのか」をやさしく整理して解説します。ぜひここで、通信の世界を支えるルールの仕組みをスッキリ理解していきましょう。
プロトコルとは?
プロトコル(Protocol)とは、コンピュータ同士が通信するときに守る共通のルールのことです。このルールがあるおかげで、異なる機器やアプリケーションでも正しくデータをやり取りできます。
たとえば、人と人が会話をするときにも、お互いに理解できる「共通の言葉」や「話し方のルール」が必要です。もし相手が英語で話しているのに、こちらが日本語で返してしまったら、会話は成り立ちません。

コンピュータの世界でも同じように、正しく情報をやり取りするには、通信相手とデータの送り方・受け取り方、順序や形式などのルールをそろえる必要があります。

こうしたルールを体系的にまとめたものが「プロトコル」であり、通信の手順やデータの構造など、やり取りの仕方を細かく定めています。
プロトコルはなぜ生まれたのか?
プロトコルが生まれたのは、異なるコンピュータ同士が正しく通信できるようにするためです。
かつてはメーカーやシステムごとに通信の方法が異なり、データを正しくやり取りできない問題がありました。1990年代にインターネットが普及し始めると、「どんな機器やシステムともつながる仕組み」が強く求められるようになりました。その課題を解決したのが、共通の通信ルールであるプロトコルです。
プロトコルの登場によって、世界中のコンピュータが同じルールで通信できるようになり、今日のインターネット社会の土台が築かれました。今では、Webページの閲覧、メール送受信、動画視聴など、私たちの身の回りの通信のほとんどがプロトコルによって支えられています。
通信プロトコルの種類
通信には目的に応じてさまざまなプロトコルが使われています。まずは、日常でよく利用される代表的なプロトコルを一覧で見てみましょう。
| プロトコル名 | 主な用途 |
|---|---|
| HTTP/HTTPS | Webページの閲覧や送受信 |
| FTP | ファイルの転送 |
| SMTP | メールの送信 |
| POP/IMAP | メールの受信 |
| DNS | ドメイン名とIPアドレスの変換 |
各プロトコルの特徴
-
HTTP/HTTPS
ブラウザがWebサーバーとやり取りするときに使う通信ルールです。
HTTPSはHTTPに暗号化(SSL/TLS)を加えたもので、安全にデータを送受信できます。ショッピングサイトやログイン画面では、主にHTTPSが使われています。
-
FTP
サーバーとパソコンの間でファイルを転送するためのプロトコルです。
Webサイトのデータをアップロードするときなどに利用されます。
-
SMTP
メールを送信サーバーに届ける際に使われるプロトコルです。
GmailやOutlookなどのメールサービスでも、この仕組みが使われています。
-
POP/IMAP
メールを受信するためのプロトコルです。
POPは端末にメールを保存、IMAPはサーバー上でメールを管理する方式です。スマートフォンやPCの複数端末で同じメールを確認できるのは、IMAPによるものです。
-
DNS
「example.com」のようなドメイン名を、通信に必要なIPアドレスに変換します。
この変換によって、私たちは数字の羅列を覚えなくても、Webサイトにアクセスできます。
このように、目的に応じたプロトコルが使い分けられて、コンピュータ同士がスムーズにやりとりできるようになっています。
プロトコルの役割:TCP/IPモデル
プロトコルの役割は、ネットワーク通信を正しく行うためにデータのやり取りを分担して処理することです。
その仕組みを整理したのが「TCP/IPモデル」と呼ばれる考え方で、通信の流れをいくつかの層に分け、それぞれの層が異なる役割を担っています。
TCP/IPモデルの階層
TCP/IPモデルは4つの層で構成され、それぞれがデータを届けるための役割を分担しています。
| 層の名前 | 主なプロトコル | 役割 |
|---|---|---|
| アプリケーション層 | HTTP/HTTPS、FTP、SMTP、DNS | Webページの閲覧やメール送受信など、ユーザーが使うアプリの通信を担当する |
| トランスポート層 | TCP、UDP | データを分割して順番通りに届け、届かない場合は再送する |
| インターネット層 | IP | 相手の住所(IPアドレス)を確認し、目的地までの経路を決定する |
| ネットワークインターフェース層 | Ethernet、Wi-Fi | ケーブルや電波を使って実際にデータを送受信する |

このように、各層がリレーのようにバトンを渡しながらデータを処理し、最終的に相手のコンピュータへ情報を届けています。
▼通信の仕組みや流れについて、以下の記事で詳しく解説しています。
-
初心者向け!図解で説明する通信のカプセル化
-
自分のPCからインターネットのWebサイトに繋がるまでのプロセス
OSI参照モデルとTCP/IPモデルの関係
TCP/IPモデルの考え方は、「OSI参照モデル」という国際標準をもとにしています。OSIモデルでは7つの層に分かれていますが、役割の基本構造はほぼ同じです。
初心者が学ぶうえでは、「上から下に向かってデータが流れ、各層で特定のプロトコルが働く」というイメージを持つだけで十分です。OSIモデルは詳細な規格を示すもので、TCP/IPモデルはそれを実際の通信に合わせて簡略化したものです。

▼TCP/IPモデルやOSI参照モデルについては以下の記事で詳し解説しています。
-
TCP/IPモデルとOSI参照モデルの違いと実際の利用シーン
-
【図解】TCP/IPとは?仕組みをわかりやすく徹底解説!
-
【初心者必見】OSI参照モデル アプセトネデブで覚えよう
身近な事例で見るプロトコル
プロトコルは、私たちが普段使っているサービスの中にもたくさん使われています。
-
Web会議ツール(Zoom、Teams など)
映像や音声をリアルタイムでやり取りするために、RTP(Real-time Transport Protocol)や SRTP(Secure Real-time Transport Protocol)が使われています。
-
通話アプリ(Skype など)
Skypeでは、P2P(ピア・ツー・ピア)通信と呼ばれる仕組みが使われています。利用者同士が直接データをやり取りするため、中継サーバーを介さずスムーズな通信が可能です。音声や映像のやり取りにはVoIP(Voice over IP)と呼ばれるプロトコルも利用されています。
-
メッセージアプリ(LINE、Slack など)
テキストメッセージやスタンプ、画像などを素早くやり取りできるように、HTTPSやWebSocket(リアルタイム通信に使われるプロトコル)が活用されています。
-
オンライン決済
クレジットカード情報などの重要なデータを安全に送るために、TLS(Transport Layer Security)という暗号化プロトコルが使われています。これはHTTPS通信の中でも特にセキュリティを強化するための重要な技術です。
このように、プロトコルは私たちの日常的なデジタル体験を支える技術となっています。
この記事で学んだこと
この記事では、プロトコルの基本から役割、そして身近な活用例までを紹介しました。
プロトコルとは、コンピュータ同士が正しく通信するための共通ルールです。このルールがあることで、異なる機器やアプリケーションでもデータを正確にやり取りできます。
本記事で学んだ内容
本記事では以下を学びました。
- プロトコルの種類
- TCP/IPモデルにおけるプロトコルの役割
- SkypeやLINEなどにおけるプロトコルの活用例
通信の仕組みを理解することは、ネットワークの基礎を学ぶ第一歩です。今後は「HTTP」や「TCP/IP」など、個々のプロトコルを学ぶことで、インーネットの仕組み全体への理解がより広がります。
参考資料
以下のリンクは、この記事で説明した手順や概念に関連する参考資料です。より詳しく学びたい方は、ぜひご覧ください。
-
Wikipedia - 通信プロトコル
-
アイティーエム - TCP/IPとは?通信プロトコルの階層モデルを図解で解説
-
イラスト図解式 この一冊で全部わかるネットワークの基本
著者:福永 勇二
定価:1,848円/192頁/ISBN:978-4-7973-8667-7
発売日:2016年3月29日/発行元:SBクリエイティ
【番外編】USBも知らなかった私が独学でプログラミングを勉強してGAFAに入社するまでの話
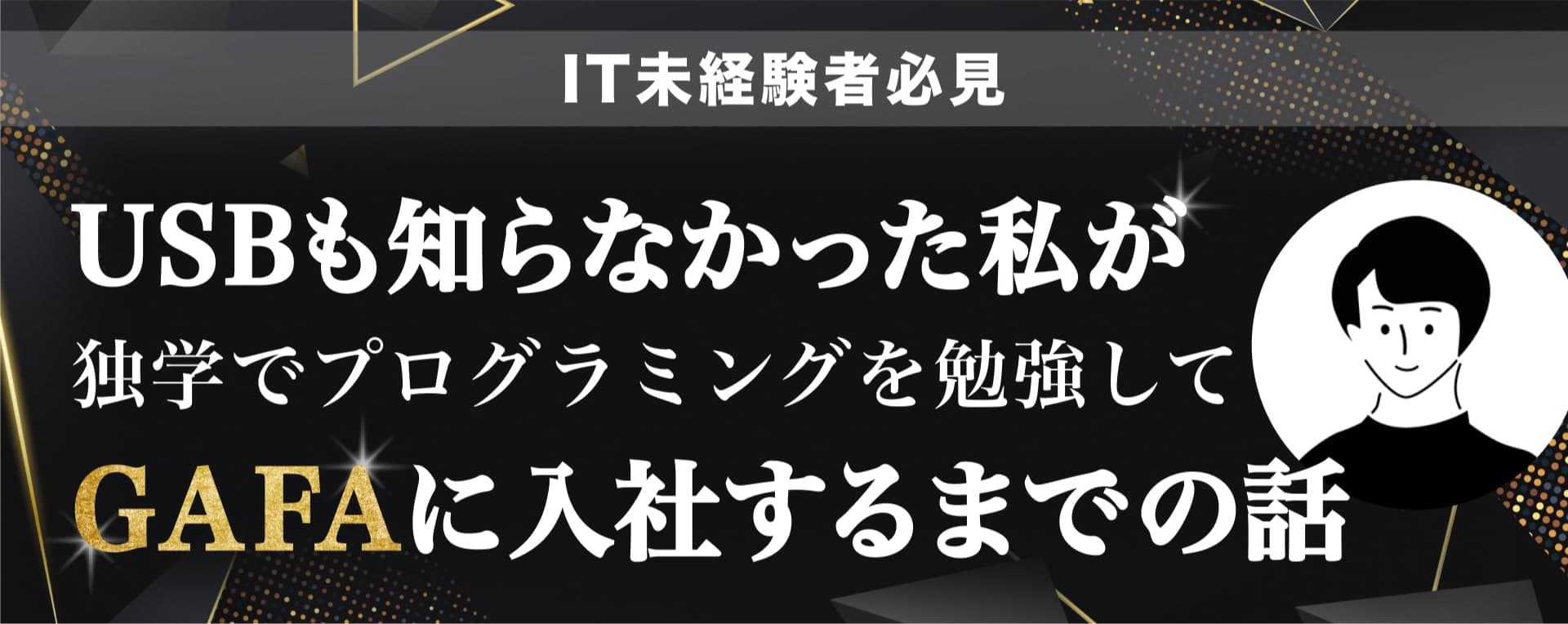
プログラミング塾に半年通えば、一人前になれると思っているあなた。それ、勘違いですよ。「なぜ間違いなの?」「正しい勉強法とは何なの?」ITを学び始める全ての人に知って欲しい。そう思って書きました。是非読んでみてください。
「フリーランスエンジニア」
近年やっと世間に浸透した言葉だ。ひと昔まえ、終身雇用は当たり前で、大企業に就職することは一種のステータスだった。しかし、そんな時代も終わり「優秀な人材は転職する」ことが当たり前の時代となる。フリーランスエンジニアに高価値が付く現在、ネットを見ると「未経験でも年収400万以上」などと書いてある。これに釣られて、多くの人がフリーランスになろうとITの世界に入ってきている。私もその中の1人だ。数年前、USBも知らない状態からITの世界に没入し、そこから約2年間、毎日勉学を行なった。他人の何十倍も努力した。そして、企業研修やIT塾で数多くの受講生の指導経験も得た。そこで私は、伸びるエンジニアとそうでないエンジニアをたくさん見てきた。そして、稼げるエンジニア、稼げないエンジニアを見てきた。
「成功する人とそうでない人の違いは何か?」
私が出した答えは、「量産型エンジニアか否か」である。今のエンジニア市場には、量産型エンジニアが溢れている!!ここでの量産型エンジニアの定義は以下の通りである。
比較的簡単に学習可能なWebフレームワーク(WordPress, Rails)やPython等の知識はあるが、ITの基本概念を理解していないため、単調な作業しかこなすことができないエンジニアのこと。
多くの人がフリーランスエンジニアを目指す時代に中途半端な知識や技術力でこの世界に飛び込むと返って過酷な労働条件で働くことになる。そこで、エンジニアを目指すあなたがどう学習していくべきかを私の経験を交えて書こうと思った。続きはこちらから、、、、
エンベーダー編集部
エンベーダーは、ITスクールRareTECHのインフラ学習教材として誕生しました。 「遊びながらインフラエンジニアへ」をコンセプトに、インフラへの学習ハードルを下げるツールとして運営されています。
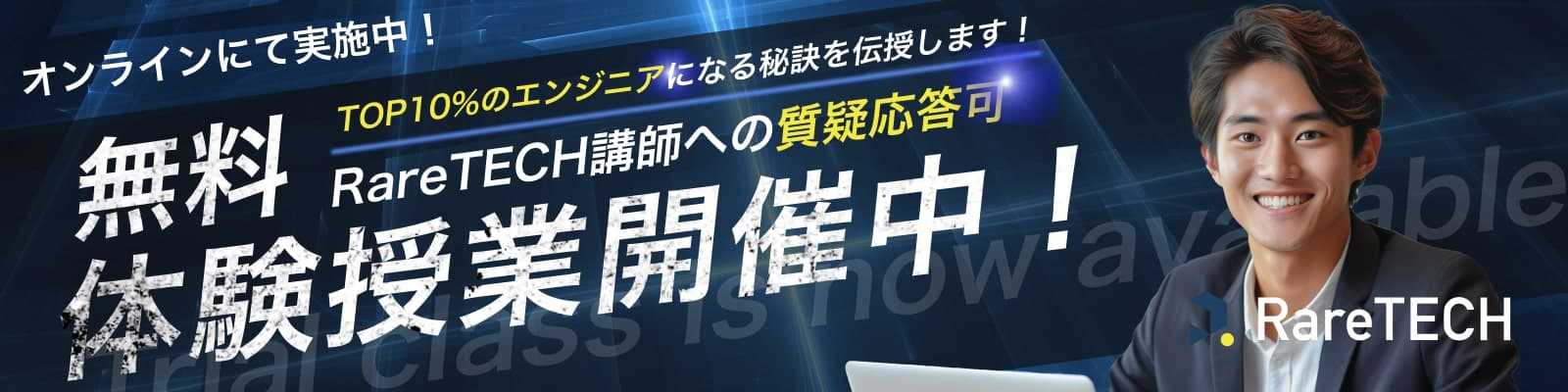
関連記事
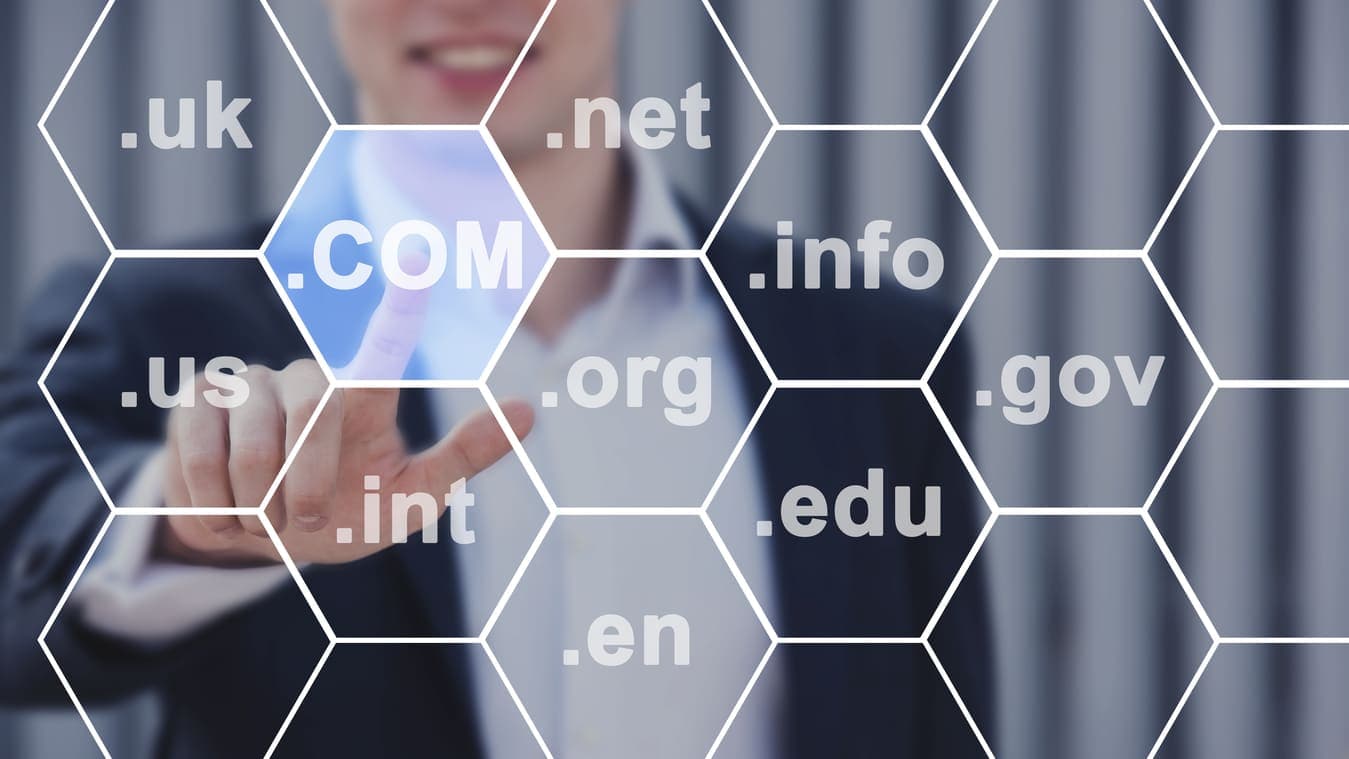
2024.09.22
EV/OV/DV SSL証明書の違いを知ろう!最適なSSL証明書の選び方
SSL証明書は、インターネット上の通信を暗号化し、第三者がデータを盗み見たり改ざんしたりするのを防ぐためのセキュリティ技術です。
- ネットワーク

2026.02.13
【図解】MACアドレスの確認方法|Windows11・macOS・iOS別に解説
MACアドレスの確認方法をWindows11・macOS・iOS別に図解で解説。各OSでの具体的な操作手順と、MACアドレスの基本的な役割を初心者向けに説明します。
- ネットワーク
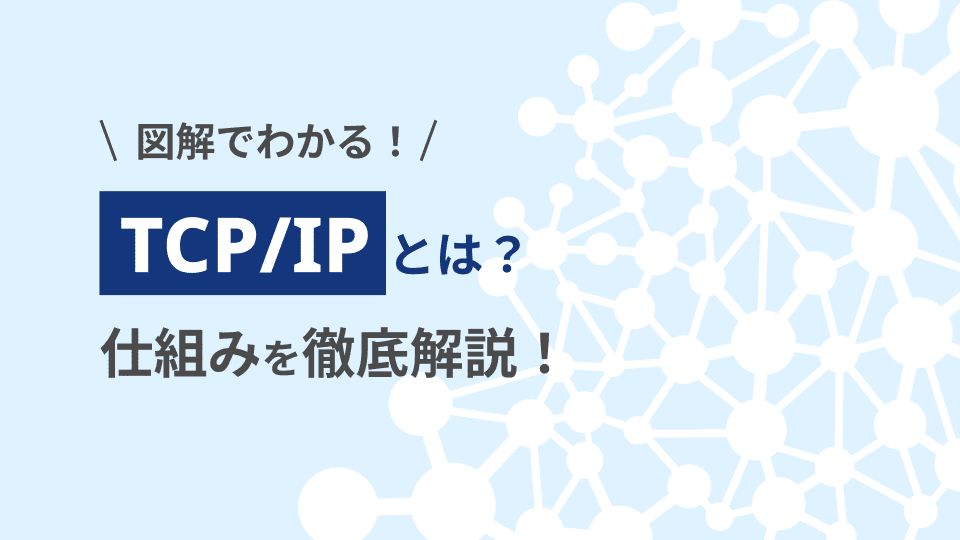
2025.11.23
【図解】TCP/IPとは?仕組みをわかりやすく徹底解説!
こちらの記事では、TCP/IPモデルの基本的な概念と構造を解説します。また、各階層の役割や機能についても詳しく説明します。
- ネットワーク

2024.03.04
【疑問解消】ただのサーバー置き場じゃない データセンターって何?クラウドとどう違うの?
この記事では、データセンターについての詳細や似た概念であるクラウドと比較した内容を解説します。
- ネットワーク