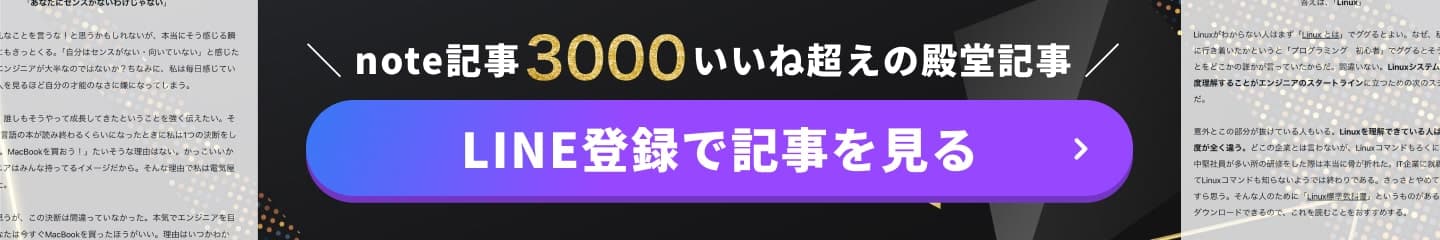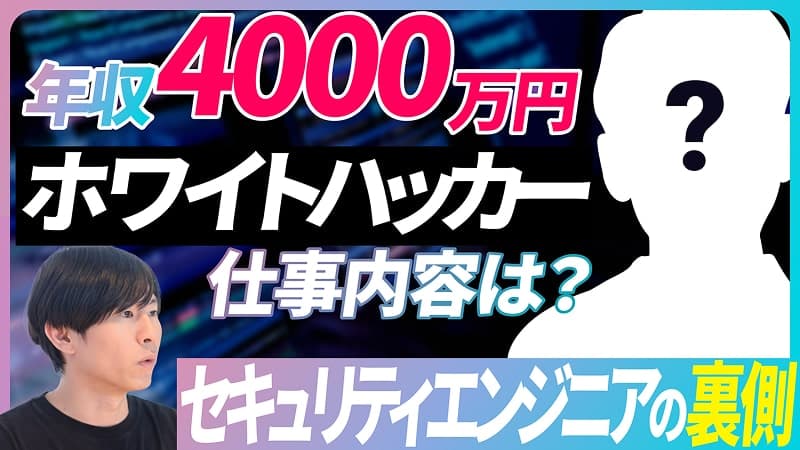はじめに
Webサービスやアプリの学習を進めていると、「REST API」や「RESTful API」という言葉を目にする機会が増えてきます。名前は知っているけれど、実際には「どんな技術なのか」「なぜ多くのサービスで使われているのか」があいまいなままになってはいないでしょうか。
REST APIとは、Webのルール(RESTの原則)に従って設計されたWeb APIのことです。URLでリソース(情報)を指定し、HTTPメソッドで操作方法を指定するシンプルな仕組みを持ち、多くのWebサービスやスマホアプリで利用されています。
この記事では、REST APIを理解するために必要な知識を順に解説していきます。まず基本となるAPIから始め、次にRESTという考え方を確認し、最後にREST APIを詳しく学んでいきましょう。
APIとは
API(Application Programming Interface)とは、アプリケーション同士が機能やデータをやり取りするための「インターフェース(接点)」のことです。
例えば、あるWebアプリが他のシステムからユーザー情報や地図データを取得したいとき、APIを通じて必要な情報を受け取ることができます。
よく使われているAPIの例として、次のようなものがあります。
- Google Maps API:地図情報を取得してWebページに表示
- 天気予報API:現在の天気や週間予報を取得
このように、APIを使うことで、他のサービスの機能を自分のアプリに組み込んだり、システム同士を連携させたりすることができます。
RESTとは
REST(レスト)とは、「Representational State Transfer」の略で、Webのしくみに沿ってAPIを設計するための4つの考え方(設計ルール)のことです。
少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、RESTはシンプルでわかりやすい仕組みを作るために考えられたルールです。ひとつずつ確認していきましょう。
1. アドレス可能性(Addressability)
インターネット上の情報は、それぞれURLで場所が決まっているという考え方です。
たとえば、「ユーザーIDが1の人の情報」は /users/1 といったURLで表すようにします。このようにすれば、どの情報を見たいのか、どのデータを操作したいのかが明確になります。

2. ステートレス性(Stateless)
RESTでは、ひとつひとつのリクエスト(命令)が独立していることが大切です。
たとえば、何かの情報を取得する時に、前回どんなリクエストを送ったかをサーバー側が覚えておくことはありません。
毎回のリクエストに、必要な情報をすべて含める必要がありますが、サーバーの構成はシンプルになり、アクセスが増えても対応しやすくなります。

3. 接続性(Connectability)
レスポンスの中に、他の情報へのリンクを含められるという考え方です。
たとえば、ある「記事の情報」を取得したときに、「この記事を書いたユーザーの情報」や「関連記事」へのリンクを一緒に返すことができます。これによって、必要な情報をたどりやすくなります。

4. 統一インターフェース(Uniform interface)
統一インターフェースとはHTTPメソッドなどあらかじめ定義・共有された方法でやり取りされることを指します。

具体的には、「GET」「POST」「PUT」「DELETE」といったHTTPメソッドを使って、以下のようにリクエストを送ります。
| メソッド | 処理内容 | 例 |
|---|---|---|
| GET | 取得 | /users/1 のユーザー情報を取得 |
| POST | 作成 | /users に新しいユーザーを追加 |
| PUT | 更新 | /users/1 の内容を変更 |
| DELETE | 削除 | /users/1 を削除する |
このようにルールを決めておくことで、どんなリソース(情報)にも同じ方法でアクセスできるようになり、使いやすいAPIになります。
REST APIとは
REST APIとは、これまでに紹介したRESTのルールに沿って設計されたWeb APIのことです。
URLで「何の情報」を操作するかを指定し、HTTPメソッドで「どのように操作するか」を決めるのが基本の形です。

たとえば、記事データを扱うREST APIでは、次のようなリクエストが考えられます。
| HTTPメソッド | エンドポイント(URL) | 処理内容 |
|---|---|---|
| GET | /articles | 記事一覧を取得する |
| GET | /articles/10 | IDが10の記事を取得する |
| POST | /articles | 新しい記事を投稿する |
| PUT | /articles/10 | IDが10の記事を更新する |
| DELETE | /articles/10 | IDが10の記事を削除する |
このようにREST APIは、「どの情報に」「どんな操作をするか」がとても分かりやすい設計になっています。そのため、開発者にとっては覚えやすく、使いやすい仕組みとなっているため、多くのWebサービスで採用されています。
REST APIとRESTful APIの違い
REST APIとRESTful APIは、どちらもRESTの考え方に沿って作られたWeb APIを指す言葉です。基本的には同じ意味として使われています。
厳密には「RESTful API」という表現は、RESTの原則に忠実な設計を強調する場合に用いられることがありますが、開発現場では区別されることはほとんどありません。
REST APIのメリット
REST APIを使うことでシンプルで効率的な開発が行えます。ここではRESTの特徴であるアドレス可能性と統一インターフェースを例に、「RESTなAPI」と「そうではないAPI」の違いを例に、メリットを見てみましょう。
RESTではないAPIの例
ユーザー情報を作成・取得・更新・削除するシステムを考えたとき、RESTの考え方を取り入れないと、処理ごとに専用のURLを作ってしまうことがあります。
例えば次のようなURLが考えられます。
/GetUser/CreateUser/UpdateUser/DeleteUser
この方法ではURLが「処理」を表しており、肝心のリソース(ユーザー情報そのもの)を示していません。そのため、URLの設計が複雑になり、操作の一貫性も失われます。

RESTなAPIの例
RESTなAPIでは、URLはあくまでリソースを表すために使います。たとえばユーザーID1の情報は /users/1 というURLで表し、操作内容はHTTPメソッドによって区別します。
GET /users/1: ユーザーID1の情報を取得POST /users/1: ユーザーID1の情報を新規作成PUT /users/1: ユーザーID1の情報を更新DELETE /users/1: ユーザーID1の情報を削除
このように、リソースはURLで一意に表現され、処理内容はHTTPメソッドに任せるため、設計がシンプルで統一的になります。開発者は「どのURLがどの情報を指すのか」を迷わず理解できるようになり、システムの利用や拡張もしやすくなるというメリットがあります。

REST APIのメリットまとめ
REST APIには、ほかにも次のような利点があります。
-
学習コストの低さ
HTTPやJSONといったWeb開発でよく使われる技術を基盤としているため、新しく習得する負担が少なく、初心者でも取り組みやすいです。
-
拡張性の高さ
サーバーが状態を保持しないステートレスな設計により、リクエスト数が増えても処理を分散しやすく、大規模な開発や運用に対応しやすいです。
-
多様なクライアントへの対応
ブラウザ、スマホアプリ、IoT機器など、さまざまな環境から同じルールでアクセスできるため、幅広いシステムに利用可能です。
-
効率的な通信
HTTPキャッシュを活用できるため、同じデータを繰り返し取得する無駄を減らし、応答を高速化することができます。
REST APIのデメリットと注意点
REST APIはシンプルで効率的な仕組みですが、いくつか注意しておくべき点もあります。
-
実装のばらつき
RESTは設計思想であり、厳密な規格ではありません。そのため、開発者やサービスごとに設計方法が異なり、APIの使い方に統一性が欠ける場合があります。
たとえば、同じ「ユーザー情報を取得するAPI」でも、あるサービスでは
/users/1、別のサービスでは/getUser?id=1のように書き方が違うことがあります。 -
複雑な操作への対応
基本的な「取得・作成・更新・削除」は表現しやすいのですが、「まとめて3人のユーザーに通知を送る」など少し複雑な処理は、単純なGETやPOSTだけでは表しにくいことがあります。その場合は、API提供者が独自の工夫を加える必要があります。
-
セキュリティ設計の必要性
REST APIは誰でも呼び出せるシンプルな仕組みのため、そのまま公開すると不正利用のリスクがあります。たとえば、認証(ログインしている人だけが使える仕組み)や権限管理(管理者だけが削除できるなど)を、APIを使う側でしっかり設計する必要があります。
これらはREST API自体のデメリットであり、利用や設計の際に注意しておきたい点です。基本を理解しておけば、実務で大きな問題になることは少なく、十分に活用できます。
まとめ
この記事では、REST APIの基本から設計のルール、メリットや注意点までを学びました。最後に、学んだポイントを整理して振り返ってみましょう。
REST APIとは、Webの設計思想であるRESTに従って作られたWeb APIです。URLでリソースを表し、HTTPメソッドで操作を指定するため、構造がシンプルで直感的に理解できます。
RESTには以下の4つの原則があり、これらに沿った設計が行われます。
-
アドレス可能性
リソースをURLで一意に表します。
-
ステートレス性
それぞれのリクエストが独立して処理されます。
-
接続性
レスポンスに他のリソースへのリンクを含められます。
-
統一インターフェース
HTTPメソッドを共通ルールとして利用します。
現代のシステム開発では、外部サービスとの連携が前提となることが多く、その中でもREST APIは最も広く利用される方式です。基本を理解しておくことで、API設計やサービス連携がスムーズになり、実践的な開発に役立ちます。
次のステップとしては、実際に自分でREST APIを作ってみるのがおすすめです。以下の記事では、初心者でも簡単に環境構築から学べる方法を解説しています。実際に手を動かすことで、今回学んだ知識をさらに深めることができます。
Fast APIでREST APIを作ってみよう 初心者でも簡単にできる環境構築から解説
https://envader.plus/article/333
参考資料
以下のリンクは、この記事で解説した手順や概念に関連する参考資料です。より詳しく学びたい方は、ぜひご覧ください。
-
Wikipedia - Representational State Transfer
https://ja.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
-
MDN Web Docs - REST
-
AWS - RESTful API とは?
-
Google Maps Platform
【番外編】USBも知らなかった私が独学でプログラミングを勉強してGAFAに入社するまでの話
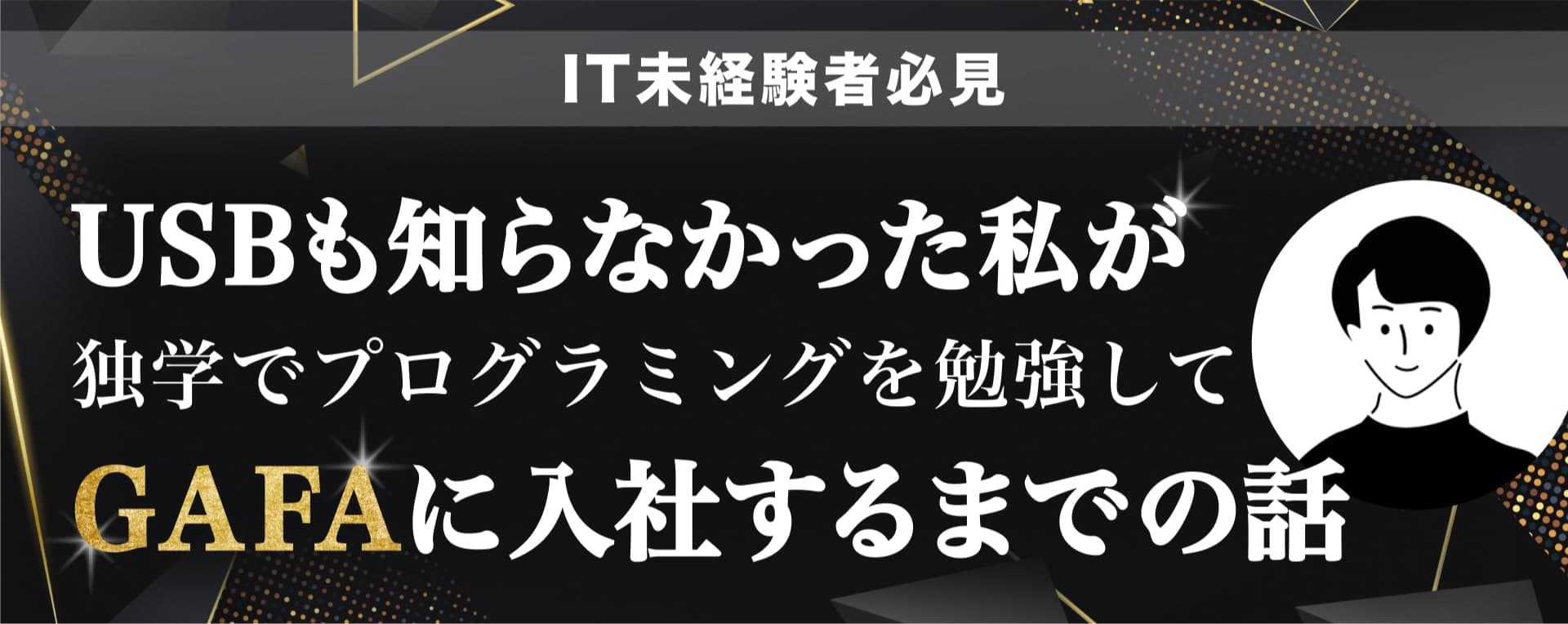
プログラミング塾に半年通えば、一人前になれると思っているあなた。それ、勘違いですよ。「なぜ間違いなの?」「正しい勉強法とは何なの?」ITを学び始める全ての人に知って欲しい。そう思って書きました。是非読んでみてください。
「フリーランスエンジニア」
近年やっと世間に浸透した言葉だ。ひと昔まえ、終身雇用は当たり前で、大企業に就職することは一種のステータスだった。しかし、そんな時代も終わり「優秀な人材は転職する」ことが当たり前の時代となる。フリーランスエンジニアに高価値が付く現在、ネットを見ると「未経験でも年収400万以上」などと書いてある。これに釣られて、多くの人がフリーランスになろうとITの世界に入ってきている。私もその中の1人だ。数年前、USBも知らない状態からITの世界に没入し、そこから約2年間、毎日勉学を行なった。他人の何十倍も努力した。そして、企業研修やIT塾で数多くの受講生の指導経験も得た。そこで私は、伸びるエンジニアとそうでないエンジニアをたくさん見てきた。そして、稼げるエンジニア、稼げないエンジニアを見てきた。
「成功する人とそうでない人の違いは何か?」
私が出した答えは、「量産型エンジニアか否か」である。今のエンジニア市場には、量産型エンジニアが溢れている!!ここでの量産型エンジニアの定義は以下の通りである。
比較的簡単に学習可能なWebフレームワーク(WordPress, Rails)やPython等の知識はあるが、ITの基本概念を理解していないため、単調な作業しかこなすことができないエンジニアのこと。
多くの人がフリーランスエンジニアを目指す時代に中途半端な知識や技術力でこの世界に飛び込むと返って過酷な労働条件で働くことになる。そこで、エンジニアを目指すあなたがどう学習していくべきかを私の経験を交えて書こうと思った。続きはこちらから、、、、
エンベーダー編集部
エンベーダーは、ITスクールRareTECHのインフラ学習教材として誕生しました。 「遊びながらインフラエンジニアへ」をコンセプトに、インフラへの学習ハードルを下げるツールとして運営されています。
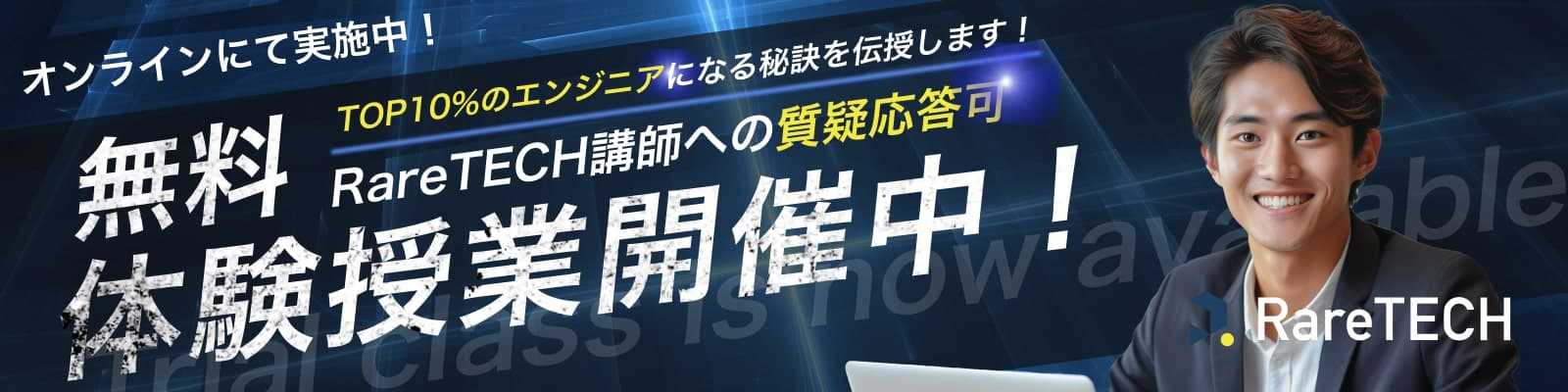
関連記事
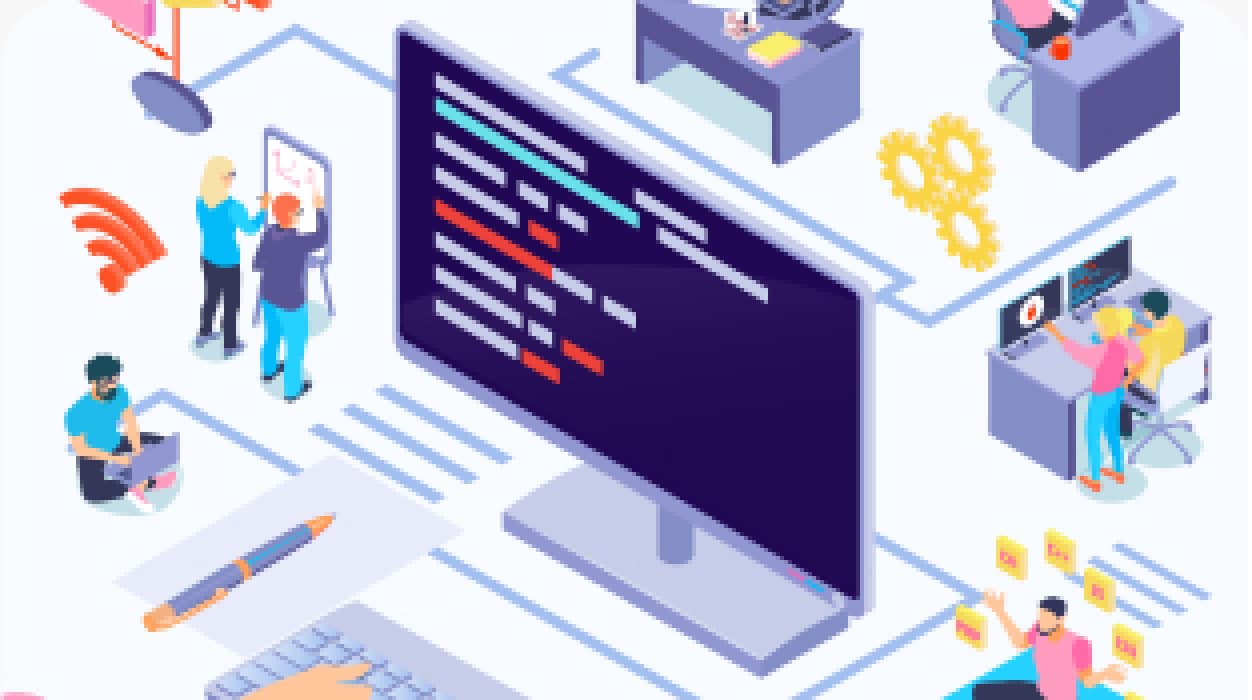
2024.03.04
インフラエンジニアに必要な資格(CCNAについて)
こちらはEnvaderの記事になります。
- ネットワーク
- インフラエンジニア

2024.08.31
AzureにはNATゲートウェイはいらない?AWSとの違いとAzureでの使いどころ
この記事では、Azureの「NATゲートウェイが不要」とされる理由を詳しく探ります。具体的には、Azureがどのようにデフォルト設定でインターネット接続を提供しているのか、その利便性や制約について解説します。
- AWS
- Azure
- ネットワーク
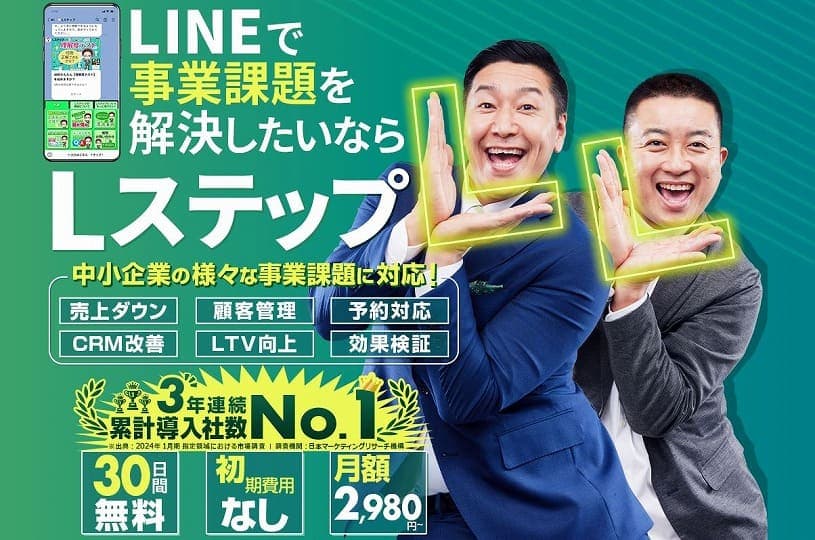
2024.02.29
Webで効果的に集客するならLステップを導入してみよう
今回は、そんな「Lステップを使ったWeb集客」について解説します。「Lステップを使ったWeb集客方法」や「Lステップを使うメリット」、「LステップでWeb集客を増やすコツ」も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- WEB

2023.01.25
Googleアナリティクスとは?基本機能や最新版GA4への移行方法解説
Googleアナリティクス(ユニバーサルアナリティクス)とは、Googleが無料で提供を行なってい*Webアクセス分析ツールです。
- WEB
- SEO